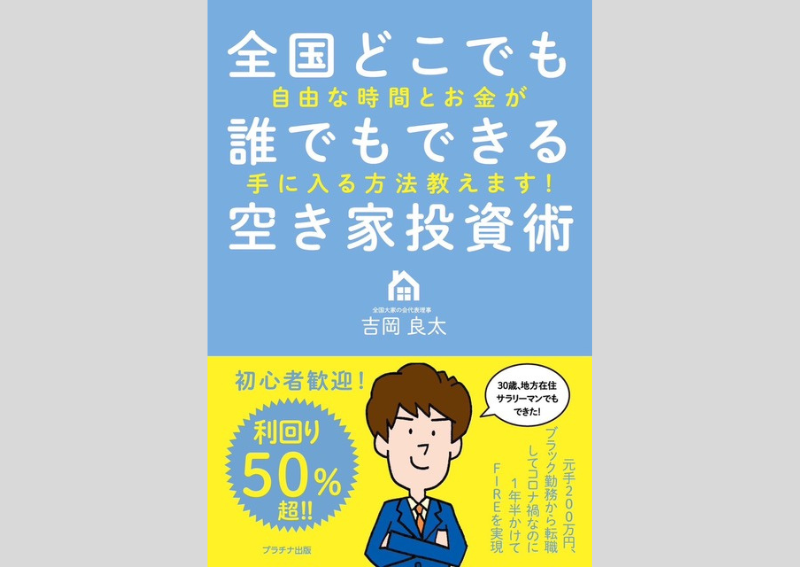企業マーケティングに浸透中の「行動経済学」を賃貸経営にも応用できるか?

2021/09/24

イメージ/©︎banphote・123RF
「ナッジ」が駐輪場を整理整頓させる
斜めに置かれたり、横を向いたり、通路に飛び出していたり……無秩序に自転車が停められていた賃貸アパートの駐輪場。その地面に、自転車1台分ごとのスペースを挟んだ「線」を引いたところ、皆がそれに従って自転車を置くようになった……。
賃貸住宅の管理に関連して、よく話題となるエピソードだ。行動経済学が語る「ナッジ」の概念に基づくマネジメントのひとつといっていいかもしれない。
ナッジ(nudge)とは、ある種の仕掛けのことだ。人間の行動を規則や強制ではなく、あくまで自発的に変えてもらうために設計される小さな工夫などのことをいう。
もっとも、ナッジはあからさまに表現されるものではない。目的に対し直接的な誘導をせず、一歩引いた、気の利いたメッセージに留めることで、抵抗や摩擦が生まれないようにする。そこが、ナッジの要は勘どころだ。
すなわち、上記アパートでは、入居者は「この線に沿って自転車を停めなさい」と、指示を受けたわけではない。
「線があるとなんとなく従っておきたくなる」「それが楽」といった、人間の行動や習慣における“ツボ”を刺激されたかたちで、おそらくは誘導されている。結果、自転車がきれいに並ぶことで、「ナッジが効いた」「成功した」ということになるわけだ。
こうした、社会に提供される具体的な方法論であるナッジのほか、行動経済学は、人間のさまざまな心理を分析し、類型化することによって、人の行動を変えたり、方向性を生み出したりするヒントを与えてくれている。
そこで、私も賃貸経営に絡めて、いくつか応用例を考えたり、集めたりしてみた。その一部を紹介していこう。
なお、以下に挙げた以外にも、行動経済学が語る人間の心理と行動に関わる原則は、さらに数多く存在する。多くのウェブサイトや本が解説しているので、「行動経済学」や「ナッジ」をキーワードに、ぜひ探してみてほしい。
「保有効果」と礼金・更新料
こちらは、実践例は見たことがない。多分、私のオリジナルの賃貸住宅オーナーへの提案だ。
例えば、「入居後、1年半を超えたら、いただいた礼金はお返しします」または「契約更新のあと、入居が1年を超えたら更新料はお返しします」と、いった契約内容を設定する。つまり、条件付き・後追いの値引きを予定しておくかたちだ。
これは、行動経済学が説くところの「保有効果」の応用となる。「すでに保有しているモノの価値は高く感じられ、手放したくなくなる」という人間の心理を突く。この例では、モノは「あとで値引きを受ける権利」となる。
「〇月〇日まで住めばまとまったお金が戻ってくる権利をせっかく持っているんだ。手放せない」―――そんな気持ちを入居者に抱いてもらうことで、「せっかく礼金や更新料をまけたのに、その後間もなく退去されてしまった」という残念なケースを抑え、入居期間をなるべく伸ばす。
すなわち、テナント・リテンション(物件が埋まっている状態の維持)を高めることが目的だ。
「同調効果」とマナー誓約書
こちらは、ほぼ似たものを実践している管理会社がある。
「この物件では、入居されている皆さんすべてが、以下の生活マナー(騒音やゴミに関することなど)を守る誓約をされています。なので、安心して暮らせますよ」
などとしたうえで、入居が決まった入居希望者に「マナー誓約書」へのサインをしてもらうのだ。
周りの意見や行動に同調したがる人間の心理、「同調効果」を利用して、物件内の生活環境を好ましい方向に誘導し、ひいてはクレームやトラブルの発生を抑えるのが目的だ。
ちなみに、冒頭に挙げた「駐輪場のナッジ」においても、この同調効果を促す側面が存在するといえるだろう。
線が引かれ、それに沿って停められている他人の自転車を見た時、「自分もそうしなければ」と、プレッシャーを感じる入居者はおそらく多いはずだ。
次ページ ▶︎ | 「返報性の原理」とウェルカム・バスケット
「返報性の原理」とウェルカム・バスケット
こちらは実行中のオーナーも多い。いわゆる「ウェルカム・バスケット」だ。
新たに入居を決めてくれた入居者のために、引っ越してきた際に当面必要になりそうな生活用品などを詰め合わせにし、あらかじめ部屋に置いておく。
中身は、歯ブラシ、石鹸、タオル、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、入浴剤、食器洗い洗剤、スポンジ、ゴミ袋……などなど。
これらをきれいにラッピングし、洒落たカゴに詰めるなどした上で、オーナーからの歓迎のメッセージも添えるのが定番のやり方だ。
あくまで純粋な気持ちを表すためのものだが、行動経済学でいうところの「返報性の原理」の発動を期待できることはいうまでもない。
返報性の原理とは、施しを受けた人が、お返しをしたくなる心理のこと。スーパーやデパ地下などでの試食が、これを刺激する方法としてよく挙げられる。
部屋を大事に扱いながら暮らしてくれたり、設備点検等さまざまなことに協力的になってもらえたりといった、オーナーにとって「助かる」入居者を生み出すためのアプローチとなるだろう。
「フレーミング効果」と長期入居率
例はほとんど見ないが、賃貸住宅としての運営上、よい数字が出ている物件ならば、それを入居者募集の際のアピールに使ってもいいはずだ。
例えば、「これまで入居者さんの9割が入居2年後も契約更新され、以降も住んでくださっている住みやすい物件です」は、入居希望者の胸におそらく魅力的に伝わるはずだ。
ただし、こうした数字を扱う際は、行動経済学が語る「フレーミング効果」について、ぜひ押さえておきたい。
上記の場合、「更新されない入居者さんは1割に留まっています」としてしまうと、同じ内容をアピールしているにもかかわらず、何となく気分が盛り上がってこない。
「生存率9割の病気」だと希望が持てるが、「死亡率1割」といわれると、なぜか不安な感じがするのと似た効果が生まれてくるということだ。
すなわち、数字はポジティブな言葉や表現に絡められるものを使い、ネガティブなそれらにくっついた方を掲げないことがポイントとなる。
この著者のほかの記事
生活保護はほとんどの人が受けている 間違えたくない文明社会での「人を別ける」線引き
「コロナ禍モード」を脱せない商業地が東京と大阪に集中――国交省の地価LOOKレポート
「一人暮らし教育」のススメ——大学や企業は賃貸住宅に住む若者に教育をするべき?
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。